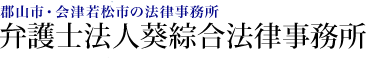子の連れ去り別居-子の引き渡しを求める方法、引渡しが認められる基準について
離婚協議中、夫婦の一方が夫婦の他方の同意を得ることなく子を連れ去り別居に至った場合、離婚するまでの間、夫婦間でどちらのもとで子を育てるか争いになることが往々にしてあります。
1 子の引き渡しを求める方法
上記のようなケースにおいて、裁判外の話し合いで争いを解決できない場合、子を実際に育てている親(子を連れて別居をした親)に対し、そうでない方の親は、子の引き渡しの調停ないし審判を申立て、子を自分のもとに引き渡すことを求めることができます(民法766条の準用ないし類推適用)。
子の引き渡しの調停ないし審判とともに監護者指定の調停ないし審判を同時に申立てることが通常です。緊急性が認められる場合には、審判の申立てに加えて審判前の保全処分を申立てることもあります。
調停では、子の引き渡しの可否は裁判所における当事者の話し合いによって決せられます(話し合いの結果、子の引き渡しについて当事者双方の合意が得られれば、子の引き渡しが認められ、合意が得られなければ子の引き渡しは認められません。)。
審判では、裁判官が当事者から提出された証拠等に基づいて子の引き渡しの可否を判断します。
2 子の引き渡しが認められる基準
(1)判断基準
審判において、子の引き渡し(及び監護者の指定)の可否は、いずれの親に監護させた(育てさせた)方が「子の利益」(民法766条1項)に適するか否かによって決せられます。
①主たる監護者(主に子を養育していた者は誰か)、②継続性の原則(子の現状の尊重)、③母性優先の原則、④監護者の適格性(監護意欲、監護能力、監護実績、住環境、監護補助者の有無等)、⑤子の事情(環境の適応状況、適応能力)、⑥子の意思、⑦きょうだい不分離の原則、⑧監護開始の態様(監護が違法な連れ去りによって開始されたか等)、⑨面会交流の受容性等が具体的判断基準となります。
(2)近時の裁判例の傾向
近時の裁判例では、子の出生時からの成育歴を全体的に見て(子の連れ去り時点を基準としない)「主たる監護者」が誰であったかが重視され、「主たる監護者」による監護に特段の事情がなければその者に子の引き渡しが認められる傾向にあるようです(参考判例等)。
逆に「主たる監護者」でない者に子の引き渡しが認められるのは、子の利益の観点から、その者を監護者とするべき特段の事情(主たる監護者の監護姿勢に著しい問題がある、子が年長で現状における交友関係等を継続する必要性が高く子自身も現状維持を望んでいる等)がある場合であるといえます。
「主たる監護者」がいずれの親であるか決しがたい場合には、子の利益の観点から、諸般の事情を考慮して、子の引き渡しの可否が決せられるようです。
〈参考判例-大阪家裁平成31年1月11日審判〉
上記認定のとおり,申立人と相手方との別居以前の主たる監護者は申立人であり,相手方の監護への関与は,休日を中心とする限定的なものであったといえる。そして,別居前の申立人の監護状況に大きな問題はない。
長男及び長女については,いずれも小学校5年生であり,いまだ日常生活において身の回りの十分な世話を必要とする年齢であるほか,今後,精神的な自立が進む年代にある。そのような時期には,これまでの成長過程を踏まえた細やかな配慮を伴う監護を行うことが特に重要であるが,そのような監護は,これまでに未成年者らと十分な愛着関係を形成している主たる監護者においてより適切に行うことができると考えられ,特段の事情がない限り,申立人を監護者と指定することが相当である。
参考文献
「子の監護者指定・引渡しをめぐる最近の裁判例について」家庭の法と裁判 第26号 2020.6.15 東京地方裁判所判事山岸秀彬
執筆
福島県弁護士会(会津若松支部)所属
葵綜合法律事務所 弁護士 新田 周作