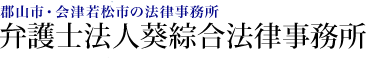どのような場合に離婚請求が認められるか
離婚の合意が得られない場合、最終的には、訴訟を提起し、判決により離婚を求めていく必要があります。
判決により離婚が認められるのは、どのような場合か、以下、説明したいと思います。
1 離婚原因
離婚原因とは、判決で離婚が認められるために必要な事情のことです。
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、判決離婚などの手段があります。
これらの離婚の手段のうち、判決離婚以外は、夫婦間の意思を基礎として成立するため、離婚原因は問題となりません(審判離婚も、その本質は裁判であるものの、夫婦のうちいずれかが異議申立をすれば失効するため、夫婦間の意思を基礎として成立しているという側面を有します。)。
判決離婚では、法で定める離婚原因がなければ、離婚は認められません。
法(民法770条1項1号~5号)で定める離婚原因は、下記のとおりです。下記離婚原因があり、婚姻関係が破綻したと認められ、離婚請求を制限するべき事由等がない場合に、離婚が認められます。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき。
2 各離婚原因の内容
(1)配偶者に不貞な行為があったとき
自由意思に基づき、配偶者以外の異性と性関係を結ぶことをいいます。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
積極的に夫婦生活を廃絶する意思に基づき、あるいは、これを認容する意思に基づき、正当な理由なく夫婦間の同居、協力義務などを怠ることをいいます。
同居、協力などの義務違反の状態は、ある程度の期間継続していることを要し、一時的な義務違反がある場合は、悪意の遺棄があるとはいえないとされております。夫婦喧嘩で一時的に実家に戻った場合には、悪意の遺棄があったとはいえません。
また、病気療養や出張、DVなどを理由とする別居は正当な理由に基づく別居として、離婚原因とならないと判断され得ます。
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
本人の生存を推定させる最後の消息があった時から3年以上生存・死亡のいずれも証明できない状態が継続していることをいいます。
生死が不明の配偶者との婚姻は、認定死亡(戸籍法89条)や失踪宣告(民法30条)によっても解消ができます。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が夫婦間の協力義務を果たせる程度に至るまでに回復可能性がないといえる程の精神的障害を有する場合のことをいいます。強度の精神病かどうかは、専門医の鑑定結果を前提として、裁判官によって判断されます。
(5)その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態をいいます。より具体的にいえば、夫婦が婚姻継続の意思を実質的に失い、別居が長期化するなどして夫婦生活を回復することが不可能であると客観的に判断できるような状態のことを意味します。
不貞行為に当たらないような行為のうち異性との過度に親密な交際や性格の不一致・価値観の相違も本号に該当し得ます。
3 裁量的棄却
民法770条2項によれば、裁判所は、離婚原因がある場合であっても、一切の事情を考慮し、離婚請求を棄却できます。この規定は、民法770条1項4号(強度の精神病)による離婚請求の場合以外では、ほとんど適用されることはありません。
4 有責配偶者からの離婚請求
(1)原則と例外
判例によれば、原則として、有責配偶者(婚姻関係の破綻を自ら作り出した配偶者)からの離婚請求は信義則に反するものとして認められず、例外的に離婚請求が認められるという判断枠組みを採用しているものと解されております。
(2)判例の判断枠組
最高裁昭和62年9月2日(民集41巻6号1423頁)は、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められるためには、下記事情が考慮されなければならないと判断しました。
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか否か。
②その間に未成熟の子が存在するか否か。
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在するか否か。
別居期間が10年程度であれば、①の要件は充たされるといわれておりますが、2年余で離婚請求を認めた判例(東京高裁平成26年6月12日)もあります。
②の「未成熟の子」とは、親の監護なしでは生活を保持できない子のことを意味します。成人した子であったとしても身体障害などにより自立できない子が「未成熟の子」と判断される場合もあります(高松高裁平成22年11月26日、東京高裁平成19年2月27日)。
執筆
福島県弁護士会(会津若松支部)所属
葵綜合法律事務所 弁護士 新田 周作