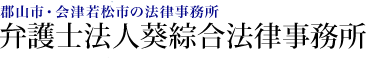特別受益とは何か
目次
1 特別受益とは 2 特別受益を考慮した具体的相続分の計算 3 特別受益の種類 (1)「遺贈」 (2)「婚姻若しくは養子縁組のため贈与」 (3)「生計の資本としての贈与」 4 持戻しの免除
相続人の中に,被相続人から生前に生活費等として多額の金銭の贈与を受けた者がいる場合,相続に際して当該相続人が他の相続人と同じ相続分を受け取るとすれば,不公平といえます。このような不公平を是正するため,「特別受益」による払戻しの制度が法律で定められています。
ここでは,特別受益とはどういう制度なのか,具体的にどのような利益の授受が特別受益にあたるのかについて説明いたします。
1 特別受益とは
特別受益とは,相続人の中に被相続人から生前に一定の目的で贈与等を受けた者がいる場合,公平の観点から,具体的相続分を算定する際に考慮される利益のことを意味します。
特別受益が認められる場合,①特別受益のうち贈与を受けた分につき相続財産額に加算して「みなし相続財産」として,②特別受益を受けた相続人について,その特別受益額を一応の相続分から控除し,残額を具体的相続分とすることになります(民法903条1項(下記参考条文))。
①の「みなし相続財産」を確定する際に,特別受益を加算するという計算上の扱いは「持戻し」と称されます。贈与の他,遺贈(遺言による財産の無償処分)は,持戻しの対象になるものの,遺贈は相続開始時に存在する相続財産の中から支出されるものであり,加算の必要がないため,特別受益のうち遺贈を受けた分については,相続財産に加算しません。
(特別受益者の相続分)
民法第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
2 特別受益を考慮した具体的相続分の計算
被相続人Aが1000万円の財産を残し,相続人が子B,C,Dの3人のみである場合,BがAから生前に贈与により特別受益200万円を受け,CがAから100万円の遺贈を受けていたとすれば,各自の具体的相続分は,下記のとおりとなります。
①みなし相続財産
1000万円(相続財産)+200万円(贈与による特別受益)=1200万円
②B~D一応の相続分
1200万円(みなし相続財産)×1/3(法定相続分)=400万円
③具体的相続分
B:400万円-200万円(生前贈与による特別受益)=200万円
C:400万円-100万円(遺贈による特別受益)=300万円
D:400万円
Bは具体的相続分の他生前贈与により200万円,Cは具体的相続分の他遺贈により100万円を取得していることから,B~DはそれぞれAから400万円の相続を受けているものと同視できます(こうして相続人間の平等が図られます。)。
3 特別受益の種類
①遺贈,②婚姻若しくは養子縁組のため若しくは③生計の資本としての贈与が特別受益となります(前記参考条文1項)。
(1)「遺贈」
遺言書に特定の不動産を「遺贈」ではなく,「相続させる」と記されている場合,当該不動産の移転を特別受益と認めてよいかが問題となります。
判例(下記参考判例)によれば,「相続させる」と記された遺言書によって特定の遺産が相続開始と同時に特定の相続人に承継され,遺産分割の対象から外れます。この点で,「相続させる」と記された遺言書も遺贈と変わりがありません。したがって,「相続させる」と記された遺言書における財産移転も遺贈と同様,特別受益として扱われます。
〈参考判例―最判H3.4.19民集45-4-477〉
「特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合・・・特段の事情のない限り,何らの行為を要せずして,被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。」
(2)「婚姻若しくは養子縁組のための贈与」
ア 婚姻・養子縁組の際の持参金・支度金
当然に特別受益に含まれると考えられております。
イ 結納金・挙式費用
結納相手の親への贈与,親みずからのために費やした挙式に関する費用であり,一般的には特別受益にあたらないと考えられています。
(3)「生計の資本としての贈与」
「生計の資本としての贈与」による特別受益があったというためには,ⓐ贈与の合意がなされたこと,ⓑそれが生計の資本としてなされたことを推認する事実が認められる必要があります。
特に,ⓑの事実の有無は,被相続人の財産状況,贈与額,贈与の趣旨,贈与の時期等の諸般の事情をもとに当該贈与が親族間の扶養義務等の範囲を超え,遺産の前渡しと認められる程度に高額であるか否かによって判断されます。
ア 通帳の払戻し
被相続人の指示で払戻し,被相続人に払戻した金員を渡した場合には,贈与の合意が認められず,特別受益を受けていたと評価することはできません。
もっとも,払戻しに近接した時期に相続人名義の口座に払戻した金額と同額の金員が入金されている場合には,贈与の事実が認められ,特別受益を受けていたと評価できる場合があります。
イ 短期間で費消される金銭の贈与
親族間の扶養的金銭援助であり,「生計の資本としての贈与」にはあたらないものが多いといえます。ただし,短期間で費消される金銭贈与が相当長期間にわたって継続的に行われ,合計金額が多額となった場合には,扶養の範囲を超えて,「生計の資本としての贈与」と評価される余地はあります(下記参考判例等)
〈参考判例―東京家審H21.1.30〉。
別表3記載の平成4年×月×日から平成6年×月×日までの間に一月に2万円から25万円の送金がなされているが,本件遺産総額や被相続人の収入状況からすると,一月に10万円を超える送金(平成4年×月×日12万円,同年×月12万円,×月×日60万円,平成5年×月×日10万円,同年×月22万円,同年×月25万円,同年×月×日10万円,同年×月×日25万円)は生計資本としての贈与であると認められるが,これに満たないその余の送金は親族間の扶養的金銭援助にとどまり生計資本としての贈与とは認められないと思慮する。また,別表1(1)の送金中の相手方が受領を認める平成8年×月×日から平成11年×月×日までの送金のうち,平成10年×月×日5万6000円,同年×月×日5万6000円,同年×月×日6万円,平成11年×月×日1万円は,いずれも一月に10万円未満であるから,親族間の扶養的金銭援助にとどまり生計資本としての贈与とは直ちに認められないと思慮するが,その余の送金はいずれも一月に10万円以上の送金がなされており,平成10年×月×日に10万円返金されたとの記載を除き返済されたと認められる証拠がないことからすると,これらの一月に10万円を超える送金(ただし,上記10万円の返金を控除する。)は生計資本としての贈与であり,いずれも相手方の特別受益と認められる。
ウ 大学の入学金や学費
将来の生活の基礎となることは明らかであるため,当然に生計の資本としての贈与にあたるとする見解もありますが,著しく多額(私立の医大の学費など)でない限り,被相続人の財産状況等に照らして,扶養義務の範囲内といえればと特別受益にあたらないと考える余地はあるものと解されます。
エ 生命保険金
生命保険金は,保険金受取人の固有財産であり,相続財産ではありません(大判S11.5.13民集15-877,大判S13.12.14民集17-2396)。また,保険金請求権は,保険契約に基づいて発生するものであるため。贈与または遺贈とはいえません。したがって,形式的に見れば特別受益にあたらないものと考えられます。
もっとも,被相続人が保険料を支払っていた場合には,保険料支払いの結果として保険金請求権を取得したものと評価し得るため,相続人間の平等の観点から,実質的に特別受益として扱うべきものと考えられます。
下記参考判例1では,①保険金の額,②この額の遺産の総額に対する比率,③同居の有無,④被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどを考慮し,民法903条(前記参考条文)の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価するべき特段の事情が存する場合には,同条を類推適用し,当該生命保険金を特別受益に準じるものと判断しました。
概ね保険金額が遺産総額の6割を超える場合は,特別受益と判断される可能性が高いものと考えられています(参考判例2)。
〈参考判例1-最判H16.10.29民集58-7-1979〉
上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
〈参考判例2〉
東京高決H17.10.27
→相続開始時の相続財産の総額約1億円のうち99%以上が生命保険金であった事例
当該生命保険金を特別受益に準じるものと判断
大阪家堺支審H18.3.22
→相続開始時の相続財産の総額約7000万円のうち6%程度が生命保険金であった事例
当該生命保険の特別受益性を否定
名古屋高決H18.3.27
→相続開始時の相続財産の総額約8400万円のうち61%程度が生命保険金であった事例
当該生命保険の特別受益性を肯定
オ 借金の肩代わり
被相続人が相続人の借金を相当額肩代わりし,相続人に対する求償権を放棄した場合には,肩代わりした借金額が特別受益と認められる場合があります(高松家丸亀支審H3.11.19)。
カ 死亡退職金
死亡退職金は,受給権者の生活保障を目的として支給されるものであるため,原則として特別受益にあたらないと考えられております。
キ 相続分の譲渡
父の相続の際,母から子へ相続分が譲渡された場合,母の相続の際に譲渡された相続分を特別受益として考えることができます(最判H30.10.19民集72-5-900)。
ク 借地権の承継・設定
被相続人に対し対価を支払うことなく借地権の承継・設定を受けた場合,借地権相当額が特別受益となり得ます(東京家審H12.3.8)。
被相続人が借地権を有する土地を相続人が底地価格で買い受けた場合には,借地権付きの土地は,借地権という制限が付されているため,その評価額は,更地価格から相当額減じられたものになります。被相続人の借地権が付いた土地を相続人の一人が地主から借地権付きの土地として相当額減価された価格で購入し,かつ,被相続人が当該借地権の消滅を許しているような場合,当該相続人は,更地を相当額減価された価格で購入したものと同様の状況となり,実質的に,被相続人から当該借地権の贈与を受けたものと評価し得ます。この場合,当該借地権相当額(土地の減価分)を特別受益と考えることもできます。
コ 土地の無償使用
(ア)土地の使用権
被相続人所有の土地上に相続人の一人が被相続人に許可を得て建物を建て,かつ,当該土地の使用に関して何ら対価を支払っていない場合,当該建物が建っているため土地が減価される一方で当該相続人は,当該土地の使用権を無償で得ることになります。この場合,当該土地の使用権相当額(土地の減価分)を特別受益と考えることができます。
使用権付きの土地を相続するのは,通常当該土地の使用権を有する当該相続人です。この場合,当該土地は,使用権付きの土地として使用権相当額の減額を受けたうえで,使用権相当額を当該相続人の特別受益として持戻すことになるので,結局当該相続人は更地で当該土地を取得したことと同じこととなり,実質特別受益の問題が生じません。
例えば,更地評価500万円・使用権相当額(土地の減価分)100万円の土地を土地使用者が相続する場合,使用権相当額100万円を特別受益として持戻し計算をしたとしても,相続する土地の評価額は更地評価500万円から使用権相当額100万円を減価した400万円となる(特別受益による持戻し分(100万円)と土地減価分による利得(100万円)が同額となる)ため,実質特別受益の問題が生じていません。
(イ)地代相当額
無償使用期間中の地代相当額が特別受益になるか問題となりますが,特別受益は,遺産の減少(前渡し)分を持戻し計算することで,相続人間の公平を図る制度であるため,遺産の減少にかかわらない地代相当額は,特別受益にあたらないものと考えられます(東京地判H15.11.17)。
サ 建物の無償使用
(ア)相続人が被相続人と同居せず,被相続人所有の建物に無償で居住していた場合
賃料相当額が特別受益となり得るか,問題となりますが,建物使用貸借は,恩恵的要素が強いこと(遺産の前渡しという要素が薄いこと),建物の使用借権は,対抗力がなく容易に明渡しが可能なため,経済的価値はないこと,賃料相当額を合計すると多額となり,過大となってしまうこと等から特別受益にあたらないものと考えることができます。
(イ)相続人が被相続人と同じ建物に同居しており,同居の相続人の占有の独立性が認められない場合
相続人は被相続人から特別の利益を受けていたものとはいえず,特別受益は問題とならないものと考えられます。特に,被相続人の療養看護のために同居が開始されたといった場合には,相続人が対価なくして建物を使用していたとはいえないため,特別受益に該当しない可能性が高いといえます。
4 持戻しの免除
被相続人は,特別受益の持戻しを免除することができます(民法903条3項)。
持戻しの免除がなされた場合には,持戻し計算をする必要はありません。
ア 持戻し免除の意思表示の方法
特別の方式はなく,明示・黙示を問いません。また,生前に行うことも,遺言によって行うこともできます。持戻しの免除の意思表示は,生前行為であっても被相続人が自由に撤回することができます。
黙示の意思表示は,下記のような事実によって推認されます。
①家業承継のために農地などの不動産を承継させる必要がある
②生前贈与の見返りとして利益を受けている
③病気などのため,独立して生計を立てられない相続人に一定の生活保障を与える必要がある
④被相続人が相続人全員に同程度の贈与・遺贈を行っている場合や全員が同程度の高等教育を受けている場合
イ 配偶者に対する持戻し免除の意思表示の推定規定
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地(配偶者居住権を含む。)について遺贈又は贈与した場合,当該被相続人については,持戻し免除の意思表示があったものと推定されます(前記参考条文4項,民法1028条3項)。
執筆
福島県弁護士会(会津若松支部)所属
葵綜合法律事務所 弁護士 新田 周作